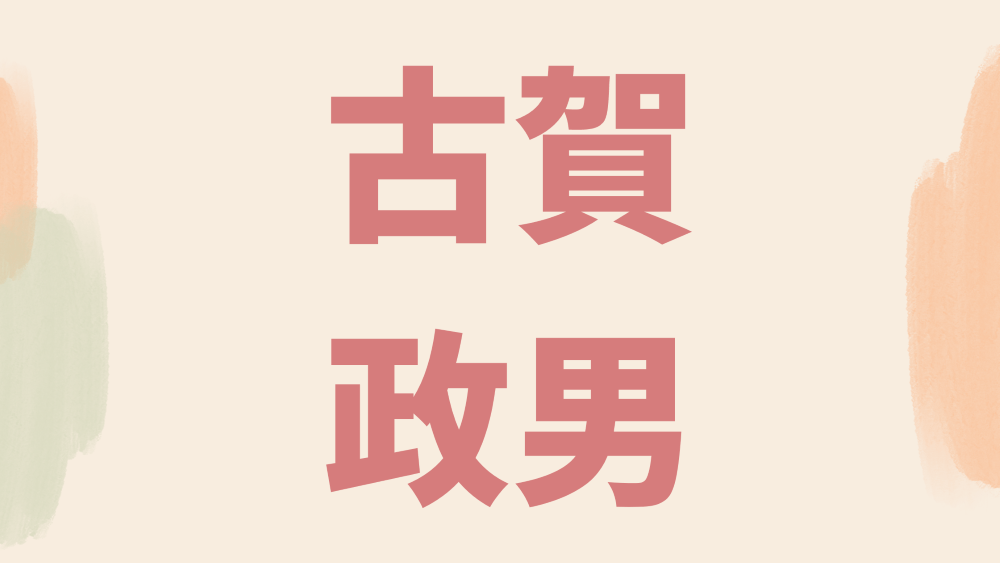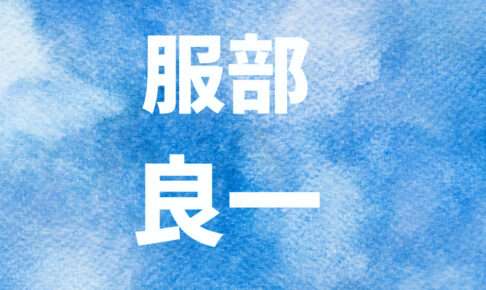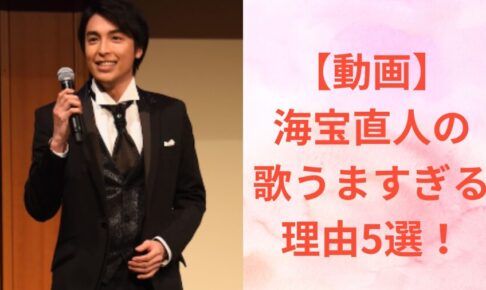古賀政男は、昭和の大作曲家、ギタリストです。
「古賀メロディー」として親しまれ数多くの流行歌を世に送り出しました。
国見栄誉賞受賞、日本作曲家協会を設立し初代会長になるなど昭和の歌謡界に多大な功績を残しました。
この記事では、古賀政男の経歴や代表曲を分かりやすく紹介します。
目次
古賀政男の経歴
古賀政男は、1904年福岡県生まれの昭和期を代表する作曲家、ギタリストです。
幼い頃、父親を亡くし長兄が暮らす朝鮮に渡り少年時代を過ごします。朝鮮統治下の高校を出た後、帰国し明治大学に入学。(1923年19歳)
明治大学ではマンドリン倶楽部の設立に参画し、在学中に「影を慕いて」を発表し音楽への才能を開花させます。
1930年(26歳)日本ビクターより「影を慕いて」を発売。
1931年(27歳)コロムビアレコードと専属契約を結び、プロの作曲家としてスタートを切ります。さっそく「酒は涙か溜息か」が大ヒット。
「酒は涙か溜息か」は藤山一郎が歌い、その後古賀政男と藤山一郎は「丘を越えて」「東京ラプソティ」など多くのヒット曲を飛ばすことになります。

ここからは、日本の歌謡界の王道を歩むことになります。
1959年(51歳)日本作曲家協会を設立し初代会長に就き20年間会長職を務めました。
また日本レコード大賞を服部良一らと制定し運営委員長として日本の歌謡界に大いに貢献してきました。
1964年(60歳)東京オリンピックのテーマソングである「東京五輪音頭」を作曲しています。
1974年(70歳)広島平和音楽祭を開催しました。
1978年(73歳)東京都代々木の自宅にて死去。
死から10日後に国民栄誉賞受賞。
古賀政男の特徴
古賀政男は、昭和の歌謡界に数多くヒット曲を残した大作曲家です。
ひと言で言うと「ザ・演歌」です。
演歌の代表曲を上げると古賀政男が作曲している曲が多くあります。何となくもの悲しいメロディーが特徴だと言えるでしょう。
これだけ日本人の心に残ったのは、おそらく戦前から戦後にかけての時代背景も関係していると思われます。
古賀政男とともに日本作曲家協会や日本レコード大賞を設立した服部良一もヒット曲を多く生み出しました。
また、数年前に朝ドラ「エール」のモデルになった同年代の古関裕而もヒットメーカーの一人でした。
ただ、当時の日本人に一番親しまれたのは、「古賀メロディー」だったと容易に想像できますし、数字にも表れています。

古賀政男の曲で最も日本人に親しまれた曲は、「影を慕いて」と「悲しい酒」です。
「影を慕いて」は、明治大学マンドリン倶楽部時代に作曲したとか。また、この曲は古賀政男が作詞もしています。
古賀政男は、作曲だけかと思っていましたが、作詞もしていたのですね。
筆者のイメージではこの曲は、演歌中の演歌だと思っていましたが、最初に歌ったのは、藤山一郎でした。
国民栄誉賞受賞、NHK紅白歌合戦の「蛍の光」の指揮者として有名。
「青い山脈」「酒は涙か溜息か」「丘を越えて」「長崎の鐘」など
「悲しい酒」は美空ひばりが歌って大ヒットした曲です。
ものすごくスローな曲で、歌唱力・表現力がないと歌いこなせない難曲です。

筆者世代では、イントロのギターの音色を聴いただけで曲を思い出す人も多いと思います。
好んで聴くことはめったにない演歌ですが、日本人としては演歌の良さも否定できないかなと思っています。
逆に音楽のひとつのジャンルである演歌を否定する人に本当の音楽好きはいないのではないかと思っているくらいです。
昭和の歌謡界で大ヒットを連発した古賀政男ですが、日本作曲家協会、日本レコード大賞を創設したり、晩年は広島平和音楽祭の実行委員長を務めるなどの活動は、人間的にも周りから信頼されていたのだろうと思います。
現代では、演歌は日本の流行歌の中では人気が凋落していくばかりですが、昭和の一時代に日本の音楽業界に大きな功績を残した古賀メロディーを一度聴いてみてください。